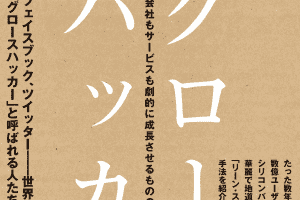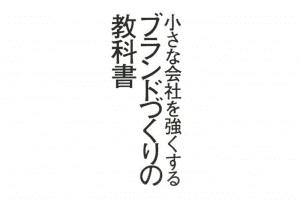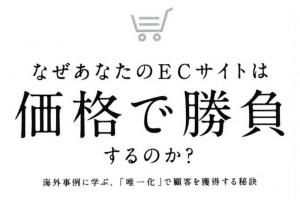いやー面白かった!Appleのデザインチームが、どうやって今の社内的地位を築いていったのかが見えてきて面白かった!
それぞれの人が、自分がやるべきことをやっていった結果なんだなぁと。ちゃんと自分の人生を生きていった結果なんだなぁと。
要約メモです。

デザインとは、ただ電子基板に皮を被せて化粧を施すことではない。消費者にどんな商品を提供して、どう彼らの生活を変えたいかに思いを巡らせることである。
アップルのデザイン部門「IDg」は、アップルの至宝として鉄のカーテンに包まれたミステリアスな部署のひとつとなっている。
ジョニーは学校で識字障害の診断を受けていた(スティーブ・ジョブズにも同じ障害があったらしい)。
父マイクの影響を正確に測ることはできないが、彼がジョニーのデザインの才能を伸ばしたことは間違いない。マイクは経験的な教育(製造とテスト)と、直感的なデザイン教育(とりあえずやってみて、その過程で手直しをしていく)の組み合わせを強く提唱していた。
ジョニーはものづくりの技能に優れていただけでなく、アイデアを伝えることにかけても並外れて優秀だった。
イギリスにもT字型デザイナーという概念がある。ひとつの専門領域を深く極めながら、同時に他の幅広い領域にも造詣を持つ人材のことだ。
デザイナーは必要なものだけをデザインすべきだというミニマリズム的な哲学は、ドイツの伝統教育の流れをくむもの。
「最終的に決めるのはクライアントだ。彼らが金を払っているんだから」だが一方で、ウィーバーはデザイナーの不満も十分に承知していた。「残念ながら、クライアントの担当者のセンスが悪いために、デザインの変更を強いられることも多い。胸を張れる作品もあるが、妥協の産物になってしまこともある」
ダービシャーはタンジェリンの基本的な考え方をこう表現した。「僕らは、デザインの質、利便性、市場性に気を配り、なにより純粋にいいものを作ろうと努力した。
デザインに「自分らしさ」を残そうとした他の事務所とはそこが違っていたとグリナーは言う。「非常に優秀でもオフィス用の工業製品しか作れないデザイナーがたくさんいた。同じ美観を大量生産の日用品に取り入れようとして、みんな失敗していた。奇妙なテクノ製品になってしまうんだ。どうしてだろう、と不思議だった。それで、製品の目的によって異なるデザイン言語が必要だということに気がついた。
「ZX75とか数字のメガバイトが名前についたコンピュータに我慢ならなかったんだ。というより、彼は90年代のテクノロジーの姿を嫌がっていた」。デザインの大きな転換期に、ジョニーは自分の道を見つけようとしていた。
「人材の採用には、スタジオが欠かせなかった。退屈な仕切り机の中でデザインなんてできない。そんなところじゃだれも働きたがらない。天井が高くて気分の高揚するようなオープンスタジオが絶対に必要だ。それがものすごく大切なんだ。それが仕事の質を左右する。やる気を生むんだ」
アップル社内で外部コンサルタントのような経営形態を保つため、ブルーナーはゆるやかな組織構造を置き、その形がおおかた今日まで続いている。進行中のプロジェクトすべてにデザイナー全員で取り組む形だ。
エンジニアが力を持つ文化だったこともやりにくかった。異なるエンジニアリング部門が、開発中の製品をブルーナーたちに渡し、外側に「お化粧」を施してもらうことだけを期待していた。
「最高のデザインを生むには、製品と共に生き、同じ空気を吸わなければならない。ジョニーのように濃密に働いていると、仕事が恋愛のようになってくる。高揚したり、落ち込んだりするんだ。だが、仕事にすべてを捧げなければ、偉大なデザインは生まれない」
彼らは、オーガニックな形、膨らみ、めずらしい色や加工のプラスチックを特徴とするヨーロッパスタイルのデザイン表現に、「エスプレッソ」という名前をつけた。それはデザイン言語というよりも、緩やかな指針であり彼らが一番いいと感じる美観だった。
コンセンサスによる製品開発が官僚的すぎることも明らかになってきた。新製品の提案には、マーケティング、エンジニアリング、ユーザー・エクスペリエンスの3種類の提案書が必要だった。
彼がアップルを追われた建国記念日の週末から、ちょうど12年が経っていた。「アップルのどこが悪いか教えてくれないか」とジョブズが問いかける。だれも返事をしないでいると、ジョブズは突然大声で怒鳴り始めた。「ブロダクトだ!プロダクトが最悪じゃないか!セクシーさがどこにもない」
ジョブズはビジネスウィーク誌にこう語っている。「すべてがシンプルになった。集中と簡素化は、私のマントラだ」
「デザインを差別化の手段だと思ってる人が多すぎる。顧客や消費者の視点じゃない。目標は差別化じゃなくて、人に愛される製品を創ることだとわかってほしい。差別化はその結果なんだ」
「怖そうなものには、ふつう手を触れない。だから持ち手があればつながりができるんじゃないかと思ったんだ。ハンドルなら触りやすい。思わず手にとってしまう。触っていいんだよ、という合図になる。それは人への従順さを示しているんだ」
革命的な製品を開発し、その後間髪をおかず次々と新たなバージョンを発表して製品をアップグレードしていく戦略だ。
ディテール作りは継続的なデザイン工程の一部であり、最後に製品の見栄えをよくするためのおまけではない。
スイッチやラッチといったデザインを際出せる細かい部品には呼び名がある。それが、「ジュエリー」だ。自動車では、ドアの取っ手やフロントグリルなどがジュエリーにあたり、同じような効果を持っている。アップルの新製品は、ジュエリーを新たな水準に押し上げた。
アップルの脅迫的な秘密主義のせいで、デザイナーはマスコミに出られず、一般に名前を知られることはなかった。彼らはあらゆるデザイン賞を総なめにし、業界の中では賞賛されていたが、普通の人たちの間ではほぼ無名の存在だった。しかし、そのことに憤慨するデザイナーはほとんどいない。チームにとってはそれがあたりまえで、ジョニーは製品が受ける評価をみんなと分かち合っている。賞をうけるときにはジョニーが代表するが、必ずチームのおかげだと言っている。
ジョニーと上層部は、安い3.5インチドライブに2ミリ足りない筐体を選んだ。「コストの節約になるハードディスクドライブを基準にせず、外観を見て決めたんです」とバスキは言う。
少なくともはじめにユーザーや批評家を驚かせたのは、電源ボタンがないことだった。どこを押しても電源が入り、しばらく使わないと電源が切れるという仕掛けは、天才ミニマリストのなせる技だった。「iPodはどこにもないような製品で、中身に説得力があったので、デザインはできるだけ簡素に絞り込み、取り除くほうがいいと思った」とジョニーは言う。
パーツが少ないことは製造誤差が少ないことを意味した。部品をぴったりとつなぎ合わせる場合、多少の誤差を許容しなければならない。部品が少なければつなぎの問題も減る。
iPodのヘッドホンケーブルも実は白ではなくムーングレーだ。
「そういうものが全部裏側についていたら、フラットスクリーンの意味がないじゃないか? それぞれの要素を本来の姿にすべきだろう」ジョブズはジョニーに言った。
ユーザーがマシンを開くことを予想して、ジョニーは内部部品もデザインすることにした。サツガーが説明する。「内部部品までやったのは、あの時がはじめてだった。マザーボードの色から始まって、コネクタやケーブルの1本1本まで僕たちが決めた。内部部品をすべてデザインしたんだ。冷却ファン容器、プレナムも作った」
もしこのプロジェクトに失敗すれば、アップルは潰れかねないと思っていた。リスクを減らすために、アップルの経営陣はヘッジをかける。平行して2種類の電話を開発し、お互いに競わせることにした。
それから2年後、マックワールドでもiPhone発表会で、ジョブズはダイヤルパッド付きiPodの画像を冗談ぽく見せた。こっちはダメな例、とジョブズが言い、観客が笑う。実際にそうなっていたかもしれないことを知る人は少なかった。
ユーザーがこのデバイスをどう「感じるか」がなにより重要だった。「デザインのはじめ、目標を定めようとする段階では、製品のストーリーについて語り合う。つまり、製品をどう見るかを話し合うんだ。その製品に何を感じるか、物ではなく感情について話し合う。
iPhoneはディスプレイがすべてだとジョニーは感じていた。縁が見えずにプールの端が海などにつながって見えるセレブな「インフィニティプール」のようなイメージを描いた。
「見事に美しく独創性のあるデザインであれば、なにもいらないことはiPodの経験からわかっていた。存在自体がものを言うんだ。それが文化のアイコンとなる」
矢継ぎ早にモデルチェンジを行うことで、アップルは「ファストフォロワー」を打ち負かしていた。ファストフォロワーとは、流行の商品を真似た安価な製品を素早く市場に送り込む企業だ。アップルは次々とアップグレードし、各世代ではるかに優れたものを作り出すことで、そうしたライバルを凌駕し続けていた。
精密加工によって製品に魔法をかける、これまでにないやり方だ。「普通なら、金属に穴を開け、LEDをはめ込んでプラスチックカバーをかぶせれば済むことだ。それで充分なのに、アップルは筐体に目に見えないような極小穴を点々と開け、穴の向こうから光が浮かび上がるように見せている。それは、工業製品への職人的な取り組みだ」
iOS7では、ソフトウェアから装飾が取り除かれ、必要最低限まで削られたハードウェアと共鳴するようになった。上品なデザインになり、特にフォント使いに趣味の良さが現れた。iOS7には、高画素のレティナディスプレイで可能となった、スイス生まれの繊細なヘルベチカ・ノイエが採用された。OS全体に印刷グラフィックデザインへの深い敬意が込められていた。
「四角いガラスは体験を提供するためのものだ。よくも悪くも、デバイスを分けるのはユーザーインターフェースだ。インターフェースの外観と反応。それは自動車にも居間にも入り込み、建築の一部となり、景色となる。それは僕たちが受け取るメディア、世界の見方、学習とコミュニケーションのあり方を変える。ユーザーインターフェースの時代がそこに来ている。
「製品開発のやり方は、2年前、5年前、10年前と今とで全く変わっていない。ほんの数人が同じやり方をしてるというんじゃない。すごく大勢の人間がみんなで同じやり方をしてるんだ」
アップルが潰れそうになったとき、ジョニーがジョブズから学んだ教訓がある。「アップルは倒産寸前でしたが、人間が死を通して生についての多くを学ぶのと同じで、私も死にかけた会社から命ある企業についてたくさんのことを学びました。もう少しで倒産という瀬戸際に立たされれば、少しはお金を儲けようと考えるのが普通でしょう。ですが、スティーブの頭にあったのは違うことでした。製品がよくなかった、だから『もっといい製品を作るんだ』というのが彼の答えでした。それ以前の再建努力とは、全く違っていたのです」
ジョニーはまた、ジョブズの一点集中の哲学を大切に思っている。ジョブズはいつも、集中とはイエスということではなく、ノーということだと語っていた。ジョニーの指導のもと、アップルは「そこそこにいい」ものであっても「偉大な製品」でなければ却下することを厳しく自分たちに課している。
ジョニーの究極の目標は、デザインを消すことだ。ユーザーがデザインを意識しないこと、それがジョニーにとって一番うれしい。「デザイナーのくせにこんなことを言うのはおかしいけれど、デザイナーがこれみよがしにしっぽを振っているような製品を目にすると、いやになるんだ。僕の目標は、シンプルなもの、持ち主が思い通りにできるものだ。デザイナーが正しい仕事をすれば、ユーザーは対象により近づき、より没頭するようになる。たとえば、新しいiPadのiPhotoアプリにユーザーは我を忘れて没頭し、iPadを使っていることなど忘れてしまうんだ」