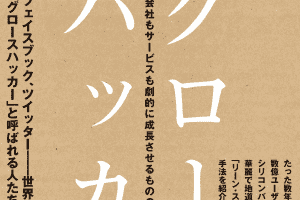「日本文化のキーワード――七つのやまと言葉」を要約メモ。
日本語は、じつに巧妙に外来の漢文や漢字を、日本語とその表記の本筋を狂わすことなく生活に取り込んだ。今また、西欧語がカタカナで日本文字化している。
本家の中国では、漢字の改良で自国の古い漢字が読めなくなったり、ハングル文字で漢字の伝統と縁が切れた朝鮮半島の人々がいま困っているときに、日本語と日本文字は、複雑なようだがきわめて柔軟に対処している。
人から物をもらったり、良いことをしてもらったときに「ありがとう」と言うのは、じつは相手の人がありがたく偉いのではない。そういう恵みをもたらしてくれた第三者の神仏のお計らいに対して、そういう宿命のなりゆきが「ありがたい」。
日本刀の刃の模様についても「匂い」という語が用いられる。刃の地肌の境目の部分に霧のようにほんのりと見える模様のこと。
「匂い」には「ひかり・威光」という意味があり、さらに人柄などの気品・おもむき、芸能・文芸の情緒・風情へと意味は広がっていく。
日本では衣のほうに香を焚きこみ、「うつし香」を楽しむ。
日本にも、すでに奈良時代には中国の唐を通じて、ペルシアから胡弓が伝来していた。ところが、日本人はこれをあまり好まなかった。弓を使ったバイオリン風の楽器はその後も入ってきているが、結果として日本に根づくことはなかった。残ったのは琵琶や三味線、鼓など、音を切っていく楽器ばかり。
間から間へと継続する緊張感を呼吸していく。呼吸が大切、息が大切。すべて気が大切という日本人の芸術の本質にはそういうものがある。
ジョン・ケージは、音の鳴っていないところにこそ、実は真の宇宙の音楽が鳴り響いているという、日本人にはわかりいいが、しかし西洋文化からすれば、じつに革命的なことをいっている。
絵についても同じことがいえる。西洋の絵は四角の額ぶちに囲まれている。その額の中をことごとく油絵の具で塗りつぶしていく。そこに完結したリアリティがあると考えられていた。しかし、東洋や日本の絵画の多くは、余白というものをきわめて大切にする。
日本の建築が、最近世界で注目されている。昔は、日本の建築というと、竹と木と紙で作られていてすぐ燃える。ペラペラで嵐が来れば吹き飛ぶ。ヨーロッパの石造りの、何百年も壊れないどっしりとしたもののほうがいいに決まっていると言われていた。
日本人は空間というものを、石や壁によって囲われたマッチ箱のようなものだとは考えていない。つまり建築とは壁でできた箱ではなく、もともと何もないもの、そこに人間が集まってはじめて人生の舞台となるものと考えた。そのためには、箱なんかなくてもいい。ただ、きっかけと「しるし」さえあればいい。それが日本人の考え方。世界の人々も、しだいにそれに気がついてきた。
欧米人には虚空に対する恐怖心があるという説がある。空というのは虚無であり、無である。無というのは怖い。神こそ「有」であり、「無」は神の不在だからである。
日本の場合は、自然に対する考え方が違う。人間は自然の中にいる。とくに何もしなくても、きっかけさえつくればみんなで「うん、あれか」ということを、ともに感じることができる。
日本の伝統芸能には、雅楽、歌舞伎、能、謡曲、狂言、茶の湯などいろいろな要素があるが、どちらかといえば、たしかに雅楽や謡曲や仕舞に現れているように、単純なリズムの緩やかなものというという印象が強い。
いずれにせよ。エネルギーがあまり感じられないというのが、現代人から見た日本の伝統芸能のイメージである。退屈だ、テンポが遅い。老人くさい、おもしろくない。
たしかに表面的にみればそうかも知れない。しかし、静かな表現の裏には、むしろ激しい否定と肯定を繰り返し、凝縮したエネルギーが秘められているのではないだろうか。
能役者が静かに舞台に立っているときの脈拍は、最高250を超えていた。